製缶加工と機械加工の違いとは?コスト・精度・納期の違いと使い分けのポイント
1. はじめに|製缶加工と機械加工の違いを知るメリット

製造業において、製品の加工方法を適切に選ぶことは、品質・コスト・納期のすべてに大きな影響を与えます。その中でも、「製缶加工」と「機械加工」は、金属加工の代表的な手法ですが、両者には大きな違いがあります。
例えば、ある工場で大型の設備フレームを製作する場合、製缶加工を選ぶのが一般的です。なぜなら、製缶加工は鉄板や鋼材を切断・曲げ・溶接することで、大きな構造物を比較的低コストで製造できるからです。一方で、精密な金属部品を作る場合には、機械加工が適しています。旋盤やフライス盤を使い、1/100ミリ単位の精度で仕上げることができるため、高い精度を要求される部品に最適です。
では、もしこの違いを理解せずに、間違った加工方法を選んでしまったらどうなるでしょうか?
例えば、強度を求められる大型フレームを機械加工で一体削り出ししようとすると、材料費や加工費が莫大に膨らみ、納期も長くなってしまいます。逆に、精密な部品を製缶加工で作ろうとすると、溶接の歪みや加工精度の問題が発生し、品質基準を満たせない可能性があります。このように、製缶加工と機械加工の違いを知らないまま加工方法を選択すると、コスト増・納期遅延・品質不良といった問題に直面することになるのです。
製造業の担当者が知るべき「加工選択の重要性」
特に、発注担当者や設計者は、加工方法の違いを理解しておくことが非常に重要です。なぜなら、設計の段階で適切な加工方法を想定しておかなければ、製造現場で無理な加工を強いられたり、追加工が必要になったりするからです。その結果、想定外のコストが発生し、最悪の場合、設計の見直しを迫られることになります。
また、加工業者に見積もりを依頼する際にも、製缶加工と機械加工の違いを理解していれば、適切な発注先を選ぶことができます。例えば、「この部品は溶接の歪みが許容されるから製缶加工で安く作れる」「この部品は高精度が必要だから機械加工の専門業者に依頼しよう」といった判断が可能になります。結果として、無駄なコストを削減し、スムーズな製造プロセスを実現できるのです。
この記事でわかること
今回の記事では、製缶加工と機械加工の基本的な違いを解説し、それぞれのメリット・デメリットを整理します。さらに、「どちらを選ぶべきか?」という視点で、用途・コスト・納期の比較を行い、最適な選択ができるようにサポートします。
この記事を読むことで、以下のような疑問を解決できます。
・ 製缶加工と機械加工の違いを簡単に知りたい
・ それぞれの加工方法のメリット・デメリットを整理したい
・ 製品の用途に応じて、どちらの加工方法を選べばよいか知りたい
・ 製缶加工と機械加工を組み合わせると、どのようなメリットがあるのかを理解したい
製造業の現場では、「この部品はどうやって加工すればいい?」といった悩みが日々発生します。この記事が、適切な加工方法を選択するための一助となれば幸いです。次の章では、まず「製缶加工とは何か?」を詳しく解説していきます。
2. 製缶加工とは?基本の特徴と加工方法

製缶加工とは?
製缶加工とは、鉄板や形鋼(H鋼・角パイプ・チャンネルなど)を切断・曲げ・溶接して組み立てる加工方法のことを指します。主に、鉄・ステンレス・アルミといった金属材料を用いて、大型の構造物や筐体(きょうたい)、フレーム、タンクなどを製造する際に活用されます。
「製缶(せいかん)」という言葉の由来は、もともと「缶(かん)=タンクや容器」を作る技術からきています。しかし、現在ではタンクだけでなく、建築・産業機械・プラント設備など、幅広い分野で利用される技術になっています。
製缶加工は、比較的大きなサイズの製品を作りやすいことが特徴であり、溶接技術を駆使して複雑な形状の構造物を作ることができます。そのため、「精密さ」よりも「強度」「形状の自由度」「コストの低減」を重視するケースに向いています。
製缶加工の主な加工方法
製缶加工には、以下のような基本的な工程があります。
① 材料の切断
製缶加工では、まず金属材料を必要なサイズに切断します。主な切断方法には、次のようなものがあります。
- シャーリング加工(板材の直線切断)
- レーザー加工(精密な形状切断が可能)
- プラズマ・ガス切断(厚板の加工に適する)
- バンドソー(帯鋸)(パイプや角鋼を切断)
材料の種類や厚みによって、適切な切断方法を選択します。
② 曲げ加工
切断した材料を、曲げ加工して立体的な形状に成形します。一般的に使用されるのは、プレスブレーキという機械で、金属板を一定の角度に曲げることができます。
厚板の場合は、ロールベンダーを使って円筒形に曲げることもあります。タンクや配管の製造では、このロール曲げ技術がよく活用されます。
③ 溶接・組み立て
製缶加工の最も重要な工程が、溶接による組み立てです。代表的な溶接方法として、以下の種類があります。
- アーク溶接(一般的な手法で、鉄骨構造に多用される)
- TIG溶接(ステンレスやアルミの薄板に適する)
- CO2溶接(半自動溶接)(大量生産向きで、作業スピードが速い)
溶接の精度が悪いと、強度不足や歪みが発生するため、熟練した技術が求められます。
④ 仕上げ加工
溶接が終わった後は、歪み取り・研磨・塗装などの仕上げ作業を行います。特に精密な寸法が求められる場合には、溶接後に機械加工を加えることもあります。
製缶加工の主な用途
製缶加工は、以下のような分野で活用されています。
✔ 産業機械のフレーム・架台(強度が求められる)
✔ 建築・土木用の鉄骨構造物(橋梁、階段、手すりなど)
✔ タンク・配管設備(プラント・化学工場など)
✔ 各種カバー・筐体(機械装置の外装部分)
例えば、大型の工作機械を支える架台や、工場で使われる設備のフレームは、多くが製缶加工で作られています。また、鉄道車両の部品や船舶の構造材にも利用されることがあります。
製缶加工のメリット・デメリット
【メリット】
・ 大きな構造物を低コストで作れる(一体削り出しよりも安価)
・ 形状の自由度が高い(溶接を活用して複雑な形状が可能)
・ 強度を確保しやすい(鋼材を組み合わせて高剛性を実現)
【デメリット】
・ 寸法精度が機械加工ほど高くない(溶接の歪みが発生する)
・ 大量生産には不向き(部品の均一性が低い)
・ 仕上げ加工が必要な場合がある(溶接後の機械加工が必要なケースも)
特に、高精度が求められる部品には不向きなため、用途に応じて機械加工と組み合わせることが重要になります。
まとめ|製缶加工の特徴を理解し、適切な用途で活用しよう
製缶加工は、大型の構造物や強度が求められる部品を作るのに適した加工方法です。溶接を活用することで、比較的低コストで製造できる点がメリットですが、精度の面では機械加工に劣るため、用途に応じた使い分けが必要です。
次の章では、機械加工について詳しく解説し、製缶加工との違いを比較していきます。
3. 機械加工とは?基本の特徴と加工方法

機械加工とは?
機械加工とは、金属や樹脂などの素材を切削・研削・穴あけなどの方法で加工し、精密な形状を作る技術のことを指します。製造業では、主に旋盤・フライス盤・マシニングセンタなどの工作機械を用いて、部品を高精度に仕上げます。
機械加工は、主に以下のような目的で使用されます。
✔ 精密な寸法が求められる部品の製造(±0.01mm単位の高精度加工)
✔ 穴あけ・ネジ加工・面取りなどの細かい加工
✔ 製缶加工後の仕上げ加工(ボルト穴や摺動部の加工)
例えば、自動車エンジンの部品や、航空機の部品などは、極めて高い寸法精度が求められるため、機械加工が不可欠です。また、製缶加工で作られたフレームに対して、ボルト穴や摺動面(すべり部分)を機械加工することで、精度を確保するケースもあります。
機械加工の主な加工方法
機械加工にはさまざまな手法がありますが、代表的なものを紹介します。
① 旋盤加工(せんばんかこう)
旋盤(Lathe)は、材料を回転させながら刃物を当てて削る加工方法です。主に円筒形の部品(シャフト、パイプ、ベアリング部品など)の製造に適しています。
- 汎用旋盤:手動で操作する一般的な旋盤
- NC旋盤:コンピューター制御による高精度加工
- ターニングセンタ:多軸制御が可能な高性能旋盤
旋盤加工は、特に軸物(シャフトやローラー)の加工に強みを持ちます。
② フライス加工(フライス盤)
フライス盤(Milling Machine)は、回転する刃物(エンドミル)を使って材料を削る加工方法です。平面加工・溝加工・穴あけなど、多様な加工が可能です。
- 汎用フライス盤:手動で操作する一般的なフライス盤
- NCフライス盤:数値制御(NC)による自動加工
- マシニングセンタ:自動工具交換(ATC)を備えた高精度機械
フライス加工は、部品の平面や溝を加工するのに適しており、精密部品の製造に不可欠な技術です。
③ ボール盤・穴あけ加工
ボール盤(Drilling Machine)は、回転するドリルを使って材料に穴を開ける加工機械です。ねじ穴やボルト穴の加工に使用されます。
- タッピング加工:ネジ穴を作る加工(M6、M8など)
- リーマ加工:穴の精度を向上させる仕上げ加工
製缶加工で作られた部品にも、ボルトを固定するための穴を後から開けることが多く、機械加工と組み合わせることで精度を向上させることができます。
④ 研削加工(けんさくかこう)
研削加工は、砥石を使って表面を滑らかにする加工方法です。高精度な仕上げが求められる部品(軸受・金型・測定器部品など)に使用されます。
- 平面研削:平らな面を高精度に仕上げる
- 円筒研削:シャフトやベアリング部品を仕上げる
- 内面研削:円筒の内側を精密に仕上げる
研削加工を行うことで、数ミクロン単位の精度で仕上げることが可能です。
機械加工の主な用途
機械加工は、精密部品や動作部品の製造に欠かせない技術です。具体的な用途は以下の通りです。
✔ 自動車部品(エンジン、トランスミッション、ブレーキ部品)
✔ 航空機部品(タービンブレード、シャフト、ベアリング部品)
✔ 半導体製造装置(高精度なフレーム・金型)
✔ 医療機器(インプラント、手術器具)
✔ 製缶加工後の仕上げ加工(ボルト穴・摺動部・ネジ穴の加工)
例えば、製缶加工で作られたフレームのネジ穴を機械加工で開けることで、ボルト締結時の精度を高めることができます。
機械加工のメリット・デメリット
【メリット】
・高精度な加工が可能(±0.01mmの精度も実現)
・一貫した品質が得られる(NC・マシニングセンタによる自動化)
・動作部品(摺動部・回転部)の仕上げに必須
【デメリット】
・コストが高い(材料を削るため、ロスが発生)
・大きな構造物には向かない(製缶加工の方が適している)
・加工時間がかかる(特に研削加工は時間がかかる)
例えば、大型の設備フレームを一体削り出しで製造すると、加工コストが高くなりすぎるため、通常は製缶加工+機械加工の組み合わせで製作されます。
まとめ|機械加工の特徴を理解し、適切な用途で活用しよう
機械加工は、精密な部品や動作部品を作るのに適した加工方法です。寸法精度が求められる部品には不可欠ですが、大型の構造物の製造には向いていません。そのため、製缶加工と機械加工を適切に組み合わせることで、コスト・精度・強度のバランスを取ることが重要です。
次の章では、製缶加工と機械加工のメリット・デメリットを比較し、用途別の使い分けについて詳しく解説していきます。
4. 製缶加工と機械加工のメリット・デメリット
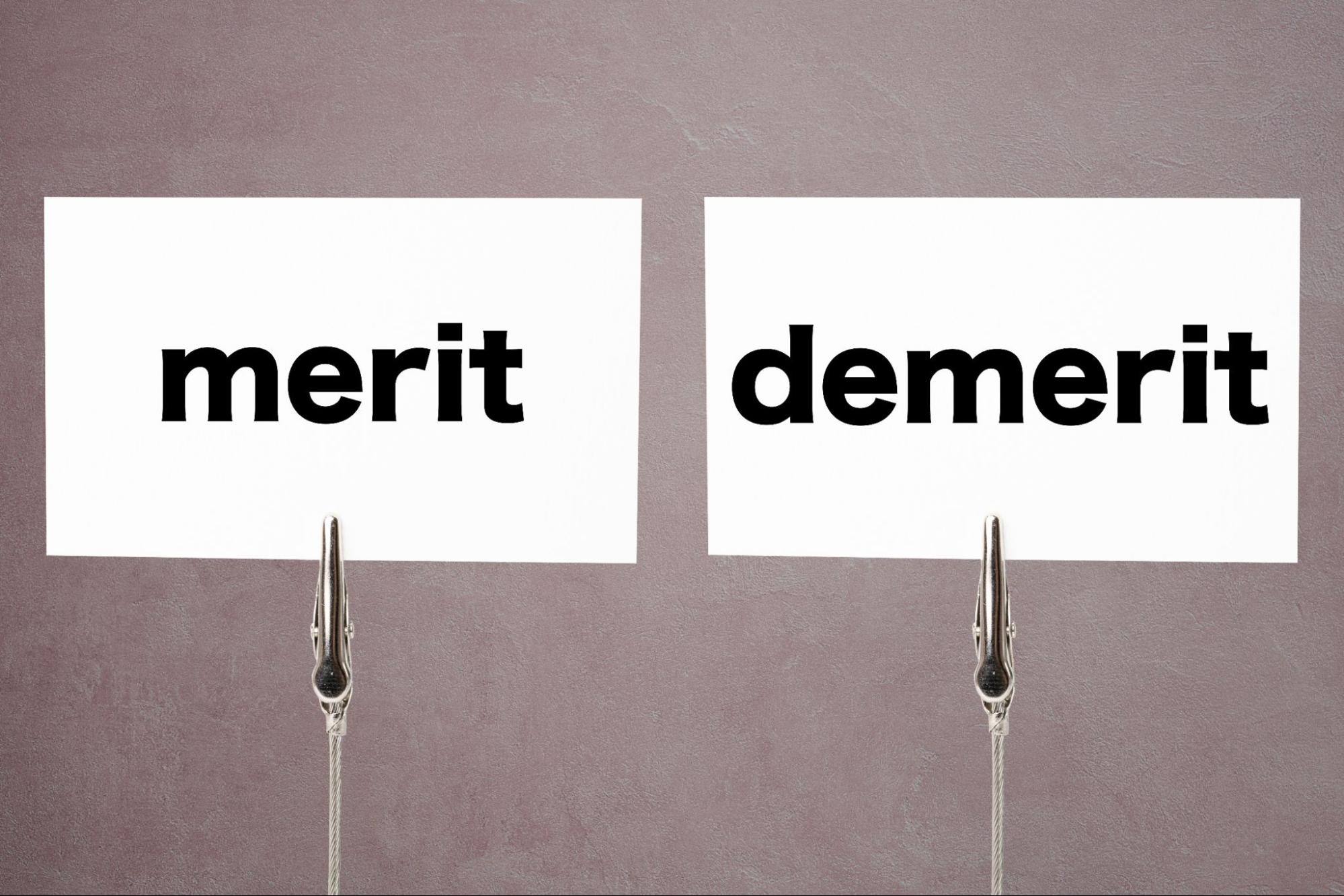
製造業において、コスト・精度・強度・納期といった観点で最適な加工方法を選択することは非常に重要です。製缶加工と機械加工は、それぞれ異なる特徴を持っており、適した用途も異なります。この章では、両者のメリット・デメリットを比較し、どのような場合にどちらの加工方法を選ぶべきかを解説していきます。
製缶加工のメリット・デメリット
【 製缶加工のメリット】
・ 大きな構造物を低コストで製作できる
製缶加工は、鉄板や形鋼を溶接して組み立てるため、大型の設備フレームやタンクなどを比較的安価に製作できます。一体削り出しに比べて材料コストが抑えられ、加工時間も短縮できます。
・ 形状の自由度が高い
溶接を活用することで、複雑な構造物を作ることができます。例えば、L字型のフレームや、複数の部材を組み合わせた特殊な形状の構造物を作るのに適しています。
・ 高い強度を確保できる
溶接によって鋼材を接合するため、荷重を分散させる設計が可能です。特に、大型の設備フレームや建築構造物など、強度が求められる部品に適しています。
・ 比較的短納期で製作できる
溶接による組み立てが主な工程となるため、機械加工と比べて短期間で製品を完成させることが可能です。
【 製缶加工のデメリット】
・ 寸法精度が機械加工ほど高くない
溶接による歪みが発生しやすく、±0.1mm以下の高精度な寸法管理が難しいことがあります。そのため、後工程で機械加工を加えて仕上げるケースもあります。
・ 溶接部の仕上げが必要な場合がある
溶接部分に歪みや凹凸が生じるため、塗装前の研磨や仕上げ作業が必要になります。特に、美観が求められる場合は追加の加工工程が必要になります。
・ 量産には向いていない
製缶加工は手作業が多いため、同じ形状のものを大量生産するには向いていません。特に、部品の均一性が求められる場合には、機械加工のほうが適しています。
機械加工のメリット・デメリット
【機械加工のメリット】
・ 高精度な加工が可能(±0.01mm単位の精度)
旋盤やフライス盤、マシニングセンタを使用することで、精密な寸法管理が可能です。特に、摺動部(スライドする部分)や軸受部など、高い精度が求められる部品に適しています。
・ 均一な品質を保ちやすい
NC(数値制御)やマシニングセンタを使用することで、大量生産時にも均一な品質を維持することができます。
・ 穴あけ・ネジ加工・仕上げ加工が得意
製缶加工では難しい精密な穴あけ加工や、ネジ切り加工、摺動面の仕上げが可能です。そのため、製缶加工後の仕上げ工程として機械加工が使われることも多いです。
・ 部品単位での加工が可能
小さな部品を精密に加工する場合、機械加工の方が適しています。例えば、ベアリングやギア、エンジン部品などは、すべて機械加工で製作されます。
【機械加工のデメリット】
・ 大きな構造物の加工には向かない
機械加工では、一体削り出しが基本となるため、大型の設備フレームや筐体を作るにはコストがかかりすぎることがあります。
・ 材料の無駄が出やすい
削り出し加工のため、材料のロスが発生します。特に、大型の部品を削り出す場合、コストが非常に高くなる可能性があります。
・ 加工時間がかかる
高精度な加工には時間がかかるため、大量生産や短納期での対応には向いていません。特に、複雑な形状の部品を機械加工で作る場合は、工程数が多くなり、製作期間が長くなります。
製缶加工と機械加工の比較まとめ
| 項目 | 製缶加工 | 機械加工 |
| 加工の特徴 | 溶接・組立 | 切削・削り出し |
| コスト | 低コスト(特に大物部品) | 高コスト(削り出しのため材料費がかかる) |
| 精度 | ±0.5mm程度 | ±0.01mmの高精度 |
| 強度 | 高い(溶接構造) | 部品単体の強度 |
| 加工スピード | 短納期 | 時間がかかる |
| 適した用途 | 大型フレーム・架台 | 精密部品・動作部品 |
どちらを選ぶべきか?用途別の判断基準
- 大きな構造物(設備フレーム・架台)を作る場合 → 製缶加工が適している
- 高精度が求められる摺動部や機械部品を作る場合 → 機械加工が適している
- コストを抑えつつ精度を確保する場合 → 製缶加工+機械加工の組み合わせ
例えば、工作機械のフレームは製缶加工で製作し、その後、ボルト穴や摺動部を機械加工で仕上げることで、強度と精度の両方を確保することができます。
まとめ|最適な加工方法を選ぶことが重要
製缶加工と機械加工は、それぞれ異なる特徴を持つため、用途に応じた使い分けが重要です。コスト・精度・強度のバランスを考慮し、最適な加工方法を選ぶことで、無駄なコストや納期遅延を防ぐことができます。
次の章では、具体的な用途別に製缶加工と機械加工の使い分けを解説していきます。
5. 製缶加工と機械加工、どちらを選ぶべき?用途・コスト・納期の視点で比較!

製造業において、製缶加工と機械加工を適切に使い分けることは、コスト削減・品質向上・納期短縮の鍵となります。しかし、どちらを選ぶべきか迷う場面も多いでしょう。この章では、用途・コスト・納期の観点から、最適な加工方法の選び方を解説します。
1. 用途別の加工方法の選択基準
まず、製缶加工と機械加工の適用範囲を整理しましょう。
【製缶加工が適しているケース】
- ・大型の設備フレームや架台の製作(例:工作機械の土台)
- ・溶接による強度が求められる構造物(例:建築用鉄骨、産業機械のフレーム)
- ・比較的低コストで製造したい場合(一体削り出しよりも安価)
【機械加工が適しているケース】
- ・高精度な部品の加工(±0.01mm単位の寸法公差)(例:シャフト、ギア、ベアリング部品)
- ・動作部品の仕上げや穴あけ・ネジ加工(例:スライドレール、摺動面)
- ・均一な品質を保つための大量生産(例:自動車部品、電子機器の精密部品)
たとえば、産業用ロボットの基礎部品は製缶加工で作り、その後機械加工でネジ穴や精密摺動部を加工するという組み合わせが一般的です。
2. コストの違い|どちらが安く作れるか?
【製缶加工の方がコストを抑えられる場合】
- ・大きな部品や厚板の加工(一体削り出しだと材料費が高騰する)
- ・多少の寸法誤差が許容される場合(溶接による歪みを考慮)
【機械加工の方がコストを抑えられる場合】
- ・小型の精密部品(大量生産時に均一な品質を保てる)
- ・追加工を最小限に抑えられる場合(最初から適した形状で加工できる)
製缶加工は材料を無駄なく使えるため、特に大型のフレームや架台ではコストメリットが大きいですが、小型部品では機械加工の方が適していることが多いです。
3. 精度の違い|どちらを選ぶべきか?
【製缶加工の精度】
- 溶接歪みにより、±0.5mm程度の誤差が発生することがある
- フレームや筐体など、大まかな寸法精度が求められる場合に適している
【機械加工の精度】
- 旋盤・フライス盤を使用し、±0.01mm単位の精密加工が可能
- 高精度が求められる部品(シャフト、ギア、ネジ穴)に最適
そのため、製缶加工後に高精度な加工が必要な場合は、機械加工で仕上げるという工程が必要になります。
4. 納期の違い|短納期で仕上げるには?
【 製缶加工の方が短納期なケース】
- 溶接と組み立てが主体のため、一体削り出しよりも短期間で完成
- 大型フレームや筐体は、削り出しよりも製缶加工の方がスピーディ
【機械加工の方が短納期なケース】
- 精密部品の一括加工が可能(NCプログラムを使えば効率的に加工)
- 追加工を最小限に抑えられる(設計段階で適切な加工方法を選べばスムーズ)
たとえば、設備フレームは製缶加工で短納期を実現し、必要な箇所のみ機械加工で仕上げることで、納期を短縮できます。
5. 具体的な使い分けの例
| 用途 | 製缶加工 | 機械加工 |
| 設備フレーム・架台 | ✔ 強度・コスト優先 | – |
| タンク・配管設備 | ✔ 防水・強度を確保 | – |
| 精密部品(シャフト・ギア) | – | ✔ 高精度が必要 |
| 摺動部(スライドレール) | – | ✔ 精密な仕上げ |
| 大量生産部品 | – | ✔ 均一な品質 |
| 製缶後の仕上げ加工 | ✔ 大枠の加工 | ✔ ボルト穴やネジ加工 |
例えば、建築鉄骨やプラント設備は製缶加工、精密部品や可動部品は機械加工が適しているという考え方が一般的です。
6. 製缶加工と機械加工の組み合わせで最適なものづくりを実現
多くの製品では、製缶加工と機械加工を組み合わせることで、コスト・精度・納期のバランスを取ることが可能です。
・ 製缶加工でフレームを作り、機械加工でボルト穴や摺動部を仕上げる(例:工作機械のベース)
・ 製缶加工で強度を確保し、機械加工で機能性を向上させる(例:プレス機の土台)
・ 製缶加工でコストを抑え、機械加工で精密な組み付け部を作る(例:ロボットアームの基礎)
このように、両者のメリットを活かすことで、より効率的なものづくりが可能になります。
まとめ|適切な加工方法を選び、最適なものづくりを実現しよう
- コストを抑えたいなら → 製缶加工が適している
- 精度が求められるなら → 機械加工が適している
- 強度が必要なら → 製缶加工が適している
- 短納期で製造するなら → 製缶加工が適している
- 精密仕上げが必要なら → 機械加工を組み合わせる
適切な加工方法を選ぶことで、無駄なコストや納期遅延を防ぎ、品質の向上につなげることができます。
